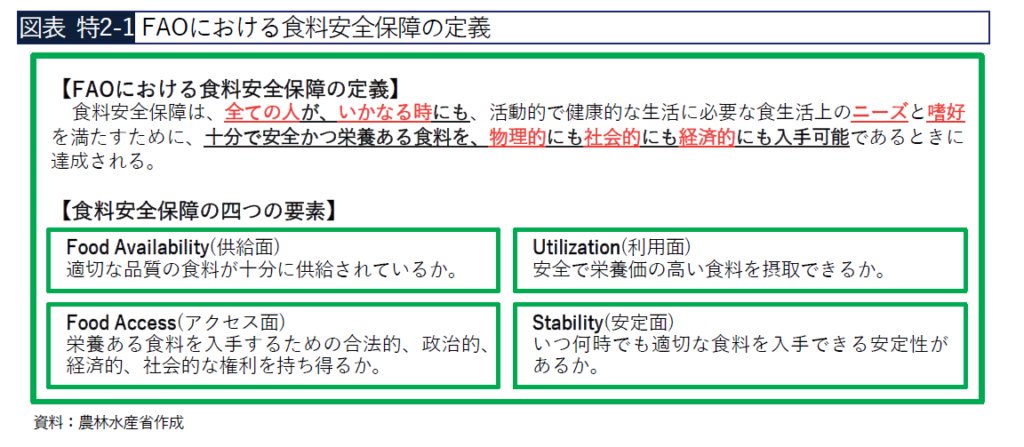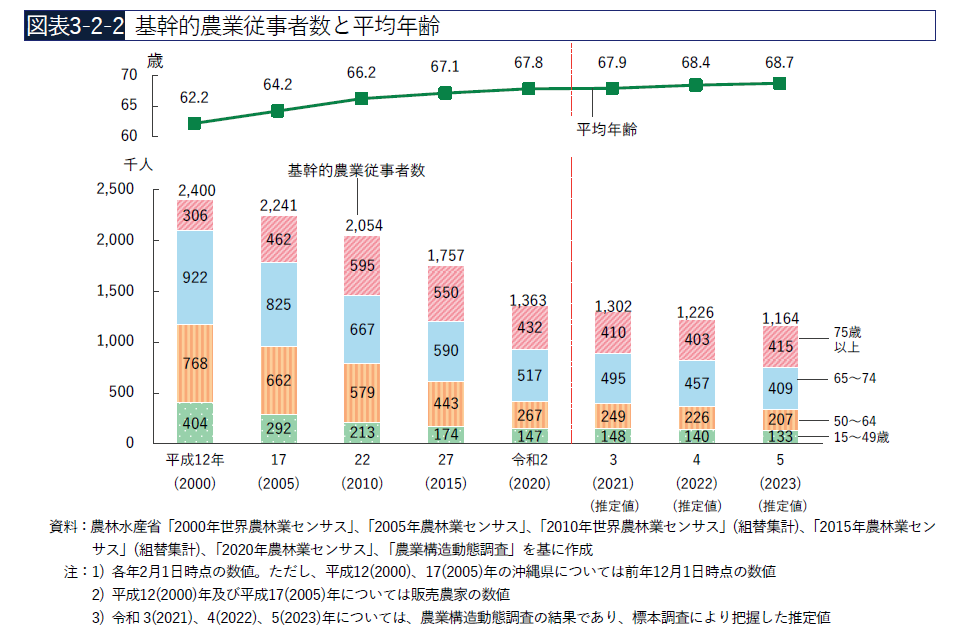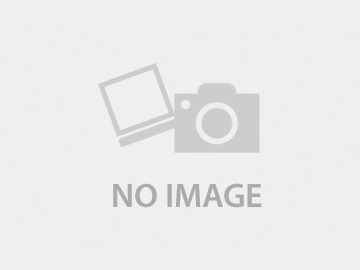#1
化学肥料の登場から現在,そして未来 −化学肥料が果たしてきた役割− 1.化学肥料の登場まで 化学肥料が商品として世に出たのは,1843年7月1日のことである。
ちなみに,わが国の無機質肥料を販売用に製造したのは,1885年に多木製肥所による骨粉の製造に始まる。
作物を栽培し収穫すると耕地の土壌から養分が収奪され,その養分を土壌に還元しないと,土壌肥沃度が低下することを経験していたからである。
そこで,土壌肥沃度の回復を自然にまかせた。
この農法を二圃式という。
そのうえ作物生産も安定しない。
耕地のまわりにある広大な共同放牧地を利用して,家畜ふん尿をとおして耕地に補給され,土壌肥沃度が維持された。
この家畜ふん尿を養分移転材料として使用するという考え方は,その後,イギリスのノーフォーク地方を中心に,当時としては最も集約的な4年輪作農法に発展していった。
#2
3)超集約的輪作−ノーフォーク農法 この農法の特徴は,共同放牧地を囲い込み,休閑を廃止してすべて耕地化し,そこへ飼料作物の根菜類(家畜用カブ)とマメ科牧草のアカクローバを導入して,飼料生産量を増やしたことである。
さらに,根菜類は土壌の堅密化を防いで土壌の物理性改善効果をもたらした。
こうして耕地の土壌肥沃度が改善された結果,この農法がいかに画期的であったかがうかがえる。
4)わが国の主要作物であるイネは水田で栽培される。
さらに水田にはかんがい水から養分が自然に補給される。
そのためイネの子実収量は,太閤検地がおこなわれた16世紀末ですでに1.8t/haと,絶頂期のノーフォーク農法によるコムギ収量と同等の生産量だった(高橋,1991)こうしたわが国の完全な養分循環システムが,土壌肥沃度の維持に大きく寄与していた。
こうした事実は,植物の無機栄養説を広く普及させたリービヒを驚嘆させたほどであった(リービヒ,2007)わが国の水田中心の農法がヨーロッパの輪作農法と決定的に違うのは,耕地の養分移転に果たす家畜ふん尿を利用して飼料畑にあった養分を堆肥という形に変えて別の耕地に移転させた。
すなわち,そもそも堆肥は養分源としての扱いであった。
#3
この試験の結果を示したのが図2である。
その結果,堆肥や化学肥料の施用量が変化しないにもかかわらず,品種の変更だけで連作コムギの平均収量のおよそ2倍以上)に増えた。
高収量品種の肥料養分への反応のよさが理解できる。
すなわち,化学肥料を与えたからといって,土壌の生物が死に絶えるなどということはない。
しかし,この黄金時代は長続きしなかった。
この不況はノーフォーク地方でも深刻だった。
しかし,飼料生産をやめ,換金作物を栽培して収益増をめざし,不況を脱出したいという要求が高まった。
したがって,問題は堆肥の代用になる養分源であった。
こうして化学肥料が受け入れられていった。
この増えつづけた人口を支えた大きな要因が,20世紀の驚異的な食料増産だった。
人類の歴史上,これほどの食料増産を可能にさせた。
面積が停滞する一方で生産量の増加傾向がつづいたのは,単収が増加したからである。
これなくして,1900年から2000年までの100年間に,人口が16億人から60億人まで増加することはなかったと述べ,食料増産に対する化学肥料には特段の問題がないようにみえる。
このため,途上国の農業者でこの技術を排除したとの厳しい批判(シヴァ,1997)がある。
#4
3.化学肥料の未来 20世紀末,1人当たりの穀物生産量が減少に 転じたとき,食料不安がひろがった。
リンやカリウムにしても,原料になる鉱石はいずれも有限の資源である。
それゆえ,化学肥料依存の食料増産が持続的でないことは明らかである。
養分移転材料を生産する家畜を飼養するための飼料畑が必要だからである。
それを打ち破る英知が求められている。